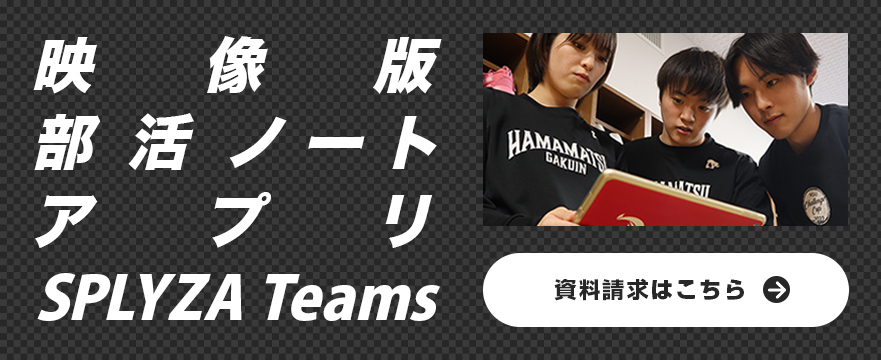【バスケットボールを通した“考える力の育成”】神奈川県立茅ケ崎北陵高校男子バスケットボール部・薬師弘明先生インタビュー
2024.12.03 written by SPLYZA Inc.
2023年度からSPLYZA Teamsを導入し、今では「描き込みランキングTOP10」に入るほどの利用率を誇る茅ケ崎北陵高校バスケットボール部。今回は、SPLYZA
Teamsの描き込み機能やクイズ機能*を活用した指導方法について、薬師先生にお話を伺いました。
*クイズ機能とは…1プレーを複数人でディスカッションできる機能です。ある描き込みに対して、該当シーンの時間に関わらず返信ができるようになっています。「伝える」だけで終わらない、コミュニケーションができる「クイズ機能」は他のどこにも無いSPLYZA
Teams独自の機能です。
**
ーSPLYZA Teamsを導入しようと思ったきっかけを教えてください。
薬師先生:
以前は、試合動画をYouTubeにアップしてからiMovieで編集し、良いプレイ集や課題プレイ集を作っていました。ただ、編集作業に非常に時間がかかっていたんです。その時、偶然SPLYZAから案内があり、試してみたところ、作業効率が格段に良くなりました。動画内に矢印を入れるようなことも簡単で、やりたいことがスムーズにできたので導入を決めました。
ー以前から映像は活用されていたと思いますが、SPLYZA Teamsを導入してどのような変化がありましたか?
薬師先生:
1つはプレイの再現性が高まったことです。成功体験がタグとして残り、それを基に共通認識が形成されるようになりました。また、課題や練習のポイントも「あの場面のあれだよね」と具体的に共有されるようになり、良いプレイと課題のプレイが明確に線引きされてきました。同じ映像を見ることで、共通言語が増えたと感じています。
ーSPLYZA Teamsを使うことで生徒の意識も変化しているのですね。具体的にはどのような形でSPLYZA Teamsを活用していますか?
薬師先生:
タグ付けは主にマネージャーが行い、選手は描き込みを通じて考えを共有する形で運営しています。たとえば「ターンオーバー」のタグを押すと、次の日にはそのシーンを確認できる状態にマネージャーが準備してくれます。これにより、選手は自分が見たいシーンを選びすぐ見られます。効率的に映像を活用した振り返りをしています。
ーなるほど。タグがついていることで、全員が同じシーンを見て共通理解が深まるのですね。編集の手間についてもSPLYZA Teamsで大幅に軽減されたようですね。
薬師先生:
はい、今までの編集作業とは比べ物にならないくらい、非常に楽になりました。

ー「描き込み機能」をよく使われているようですが。
薬師先生:
選手がその場で何を考えてプレーしているのかを知りたいというのが大前提にあります。例えば、ターンオーバーが起きたときに、単にミスとして捉えるだけでなく、選手が「どうしてそうしたのか」という意図を理解できると、そのミスも狙いがあってのものだと受け止められます。また、その狙いをもとに「こうした方が良いかもね」とプラスに変えていけます。さらに、選手が自身で何を良いプレイと考え、何を課題と感じているのかを把握するためにも、描き込みも重視する指導を行っています。
ーなるほど。選手の意図や考えが見えてきたことで、指導に活かせている部分もありますか?
薬師先生:
そうですね。選手にとってプレイは習慣のようなものなので、同じような場面が練習や試合でも繰り返し出てきます。その際に私が「今のはこうだっからこの選択をしたの?」と聞くと、選手が「そうです」と答える場面が増えました。こうして、選手の考えを理解し、寄り添えるようになってきたと感じています。
ー選手の描き込みに対して先生から返信もされていますよね。具体的にどのように活用しているのですか?
薬師先生:
まずは選手が映像を見るモチベーションが上がる工夫をしています。SPLYZAのサポートスタッフの方からKPT法を教わり、現在は実験的にそのKPT法をアレンジして、「良いプレイ=”Keep”」と「8割正解だけど別の選択肢もあった=”Try”」でタグを付けています。選手がその後動画を見返した際、自分で課題をコメントし、そこにポジティブな返信を付け加えることで、映像を見るモチベーションが上がって欲しいと思い取り組んでいます。
選手たちも部活だけじゃないので、時間がない中でも少しでも映像を見たくなるようなポジティブな活用方法にしていますね。

ーポジティブなフィードバックが映像を見る習慣の形成に繋がってきますよね。 この描き込みは選手が主体的に行っているんですね。
薬師先生:
責任感の強い生徒はもちろん取り組むのですが、「やれ」と指示されてやるだけではあまり意味がないと思います。だからこそ、自分がコメントすると必ずコーチから良い返信がもらえるという流れが習慣化されれば、自然と書きたくなるのではないかと考えています。現在はその点を実験中です。
ーまだ実験中とのことですが、その取り組みを経て少しずつ変化は見られましたか?
薬師先生:
そうですね。バスケットボールはスピード感があり、試合中に個々のプレーを細かく振り返るのは難しいのですが、この返信ができる機能を活用することで、プレーの詳細に焦点を当てたコミュニケーションが可能になります。試合後にコメントを通じてやり取りすることで、選手一人一人と向き合う時間を補完できると感じています。
この仕組みは、昔の練習ノートのような役割を果たしていて、選手との距離が近づくと同時に、自己肯定感の向上や映像を見る習慣の形成にもつながっています。部活動自体に意識が向き、「行きたい」と思える環境を作るツールとして活用できる可能性も感じています。

ー積極的に取り組んでいる選手たちにも変化はありましたか?
薬師先生:
コミュニケーションを多く取っている選手ほど、プレーにおける「正解」の数が増え、自分が良いと考えるプレーと、私たちが良いと判断するプレーが一致する機会が増えてきました。逆にミスした場合でも、「今のはダメですよね」と選手自身が冷静に振り返る姿勢が見られます。良い点も悪い点も共通の理解が深まり、両者の考える「正解」が近づいてきたと感じています。
ー共通理解が進むことで、さらに良いコミュニケーションの輪が広がっていきそうですね。ありがとうございました。