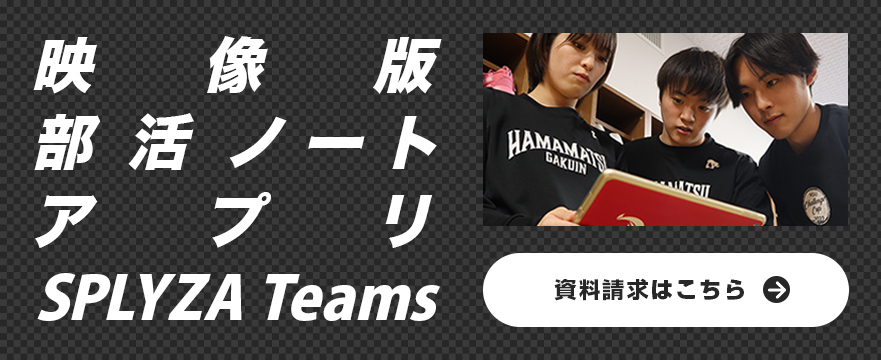サッカーの枠を越え、人生を豊かにする。中京大中京が実践する、高大連携と地域を巻き込む次世代アスリート育成のエコシステム
2025.08.18 written by SPLYZA Inc.
「気合と根性」「指導者の経験則」といった言葉が、依然として力を持つ高校サッカーの現場。しかし、選手のコンディションやプレーの質を客観的に評価し、成長を最大化するためには、科学的なアプローチが不可欠となりつつある。
伝統と革新が共存する強豪、中京大学附属中京高校サッカー部。彼らは映像分析ツール「SPLYZA
Teams」などを活用し、単なる勝利至上主義とは一線を画す、選手の「思考力」と「主体性」を育む独自の育成環境を構築している。
「状況に応じて判断・決断ができる選手になる」。大野陽介コーチが語るチームコンセプトの背景には、映像と対話を通じて選手の持つ可能性を最大限に引き出そうとする、緻密な指導設計があった。その取り組みの深層に迫る。
【課題と背景】 主観と客観の融合を目指して

すべての取り組みの根底にあるのは、「選手の視野を広げ、物事の奥まで見る習慣を身につけてほしい」という大野コーチの思いだ。
「一つのプレーに対して、見えているのは表面的な事象だけかもしれない。その奥にある原因や、次に繋がる選択肢まで思考を巡らせることで、プレーの質は大きく変わる」。
指導者が一方的に正解を与えるのではなく、選手自身が気づき、考えるプロセスを重視する。そのために必要だったのが、誰もが同じ事象を共有し、多角的な視点から議論できる「共通言語」としての映像だった。映像を介して主観と客観を融合させ、選手の自己理解を深める。それが、チームの新たな挑戦の始まりだった。
【具体的な取り組み】 データと対話で築く「成長のサイクル」

中京大中京では、映像分析が単なる「振り返り」で終わらない。選手の思考を深め、次のアクションに繋げるための仕組みが随所に組み込まれている。
1. 一つの映像を「二周」するミーティング
週に一度行われる映像ミーティングでは、同じ試合映像を最低でも二度、異なるテーマで分析するという。「例えば、一度目は『トランジションが起きた場面』を抽出します。そして二度目は、『では、なぜそのトランジションは起きたのか』『その後の行動はどうだったか』というように、一つの現象に対してグラデーションをつけながら深掘りしていくのです」と大野コーチは語る。
ポジションや学年別のグループワークを取り入れ、多様な意見を集約。指導者が提示した「正解」をなぞるのではなく、選手自らが課題を発見し、解決策を議論する場となっている。このプロセスが、主観的な感覚を客観的な視点で捉え直す訓練になる。
2. 「AだからB、そしてCへ」思考を促す対話
選手のアウトプットに対しても、思考を止めさせない工夫がある。「右のクロスがうまい」という事実の指摘で終わらせず、「なぜうまいのか」「だから、どう対策すべきか」という次の思考を促す。大野コーチはこれを「AだからB、そしてCへ」という思考の流れだと説明する。
「ある選手が『ここを決められるようになりたい』と感情をアウトプットしたとします。それに対して『じゃあ、あなたはどうするの?』と問いを返す。すると選手は、トラップの位置、その前の動き方、と具体的な改善点に思考を巡らせ始める。この思考の連続が重要です」。
指導者からのコメントや問いかけは、選手が自身のプレーをより深く、構造的に理解するための「きっかけ」として機能している。
3. サッカーの枠を越えた多様な専門性の導入
同校の取り組みは、ピッチの中だけに留まらない。フットサルFリーグの強豪・名古屋オーシャンズと提携し、そのスタッフによる講習会を月1回開催。サッカーとは異なる視点から、狭い局面での技術や戦術を学ぶ。
さらに、系列である中京大学との連携も強みだ。大学の専門トレーナーが週1回フィジカル指導にあたり、定期的に大学の施設でフィジカルチェックを実施。科学的根拠に基づいたコンディション管理と強化が行われている。
「こうした環境が、選手たちのキャリア観にも影響を与えています。近年、トレーナーを目指す選手や、大学で学生コーチを志す選手が増えてきました。プレーするだけでなく、多様な形でサッカーに貢献したいという意識が芽生えています。」と大野コーチは変化を語る。

【成果と変化】 チームを取り巻く「エコシステム」の醸成

これらの取り組みは、単に選手のプレーを向上させるだけでなく、チームを取り巻く文化そのものを変えつつある。
上級生が下級生にSPLYZA
Teams(映像分析ツール)の使い方をレクチャーする文化が自然と生まれ、選手間での知識の継承が進む。約65名という少数精鋭の部員たちは、カテゴリーの垣根を越えて交流し、互いに学び合う良好な関係を築いている。
また、「誰かの何かのきっかけに」というスローガンの下、高校生が主体となって近隣の小学生向けにサッカースクールを開催。地域に開かれた存在となることで、選手たちはサッカーを通じて社会と関わる経験を積む。
選手、指導者、そして彼らを支える保護者の間にも、強い信頼関係が見られる。「Aチームの保護者の方が、自分の息子が出ていないBチームの試合を観に来て『Bチームも頑張ってください』と声をかけてくれる。選手だけでなく、保護者も含めた全員で戦っている感覚があります」と大野コーチは言う。
選手、指導者、保護者、大学、地域、そしてスポンサー企業。それぞれが有機的に繋がり、選手の成長を多方面から後押しする一つの「エコシステム」が、そこには形成されている。
まとめ:サッカーを通じて「人生を豊かに」

中京大中京サッカー部の取り組みは、目先の勝利だけを追うものではない。データと対話を駆使して選手の思考力を鍛え、多様な専門性や社会との関わりに触れる機会を提供することで、サッカーという競技の枠を越えた「選手の成長の最大化」を目指している。
「サッカーを通じて人生を太く、楽しくしていく。そのきっかけを見つけられるのがうちの魅力。全国トップクラスの他競技のアスリートからも刺激を受けられるこの環境が、本当に羨ましい」と大野コーチは笑顔を見せる。
ここで得られるのは、サッカーの技術だけではない。自ら課題を発見し、仲間と議論し、解決のために行動する力。それは、変化の激しい未来を生き抜く上で、最も価値のある資産となるはずだ。サッカーに本気で向き合いたい、そして人間として大きく成長したいと願う中学生にとって、これ以上ない環境がここにはある。